
野村 典文 教授
長年の経験と最新のAI時代を
超えた最強タッグ!
担当予定科目:
ソフトウェア工学
情報エンジニアリング概論
データベース
計算機概論
専門分野:
コンピュータサイエンス、ソフトウェア工学、要求工学
受験生へ一言
未来を創る若者へ、人間中心の争いのない、地球環境にやさしい世界をコンピュータテクノロジーで作り上げよう!そのために私たちは、君たちを最強にしてみせる。
先生に聞いてみました!
どんな研究をされていますか?
コンピュータが思った通り動くためには、コンピュータに命令を出すソフトウェア(プログラム)が必要になります。そのソフトウェアが効率よく、正しく動くためのデザイン(設計)方法を研究しています。専門的な言葉でソフトウェア工学と呼ばれています。


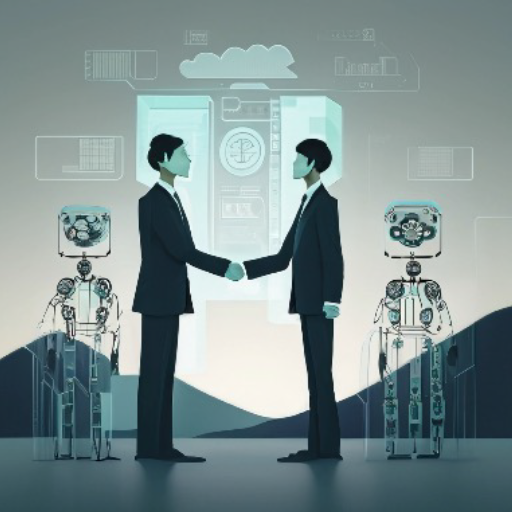
なぜそうした研究に関心を持たれたのですか?
最近はデジタル・トランスフォーメーション(DX)という言葉が使われています。DXとは、世の中の様々な事象を、コンピュータ技術を使ってデジタル化し、今まで解決できなかった多種多様な課題を解決しようという動きです。例えば、働き手が不足してモノがタイムリーに運べなくなる物流問題があります。この問題をデジタル技術で解決する取組に、ドローン配送や自動運転とロボットを組み合わせた配送などがあります。


DXを実現する際に重要となるのは、顧客価値を高めることです。では、顧客価値とは何でしょう。それは、顧客との共感です。顧客が心から共感してくれれば製品やサービスは多くの人に使われ、多くの人を幸せにします。そのために、顧客との共感を可視化(どれだけ顧客が共感したかを客観的に表現する)するソフトウェアを研究しています。仮想空間を利用した顧客体験をデザインすることもその一つです。

授業では何を担当されていますか?先生の授業の強みを教えてください。
情報エンジニアリング概論やソフトウェア工学などを担当しています。
これらの授業では、物事の正しい筋道を考える思考方法と社会の役に立つソフトウェアの全体構造設計(アーキテクチャ設計)方法を学びます。
授業の最初に、社会や企業のビジネスに関する構造を可視化する方法を学びます。なぜなら、コンピュータ技術を上手に活用するためには、社会構造や企業ビジネスの構造を知る必要があるからです。そして、社会構造や企業ビジネス構造にコンピュータ技術を上手に組み込むための設計技術を学んでいきます。
私は、この授業を受けることで、これからのデジタル社会に価値をもたらすための思考方法やデザイン技術が身に着き、皆さんがコンピュータ技術を正しく使う人材に育っていくことを確信しています。
情報科学って何の役に立つのですか?
皆さんはスマートフォンが使えなくなったら、結構生活に困りますよね。友人とのコミュニケーションも滞りますよね。実は、スマートフォン(スマホ)はコンピュータ技術で作られているのです。LINEなどのチャット、SNS、TikToKなど、スマホで動作するアプリケーションも、すべてコンピュータ技術で作られています。
また、世の中の生活基盤や企業活動のほとんどに、コンピュータ技術が使われています。
このコンピュータ技術は情報科学が生み出したものです。新たなコンピュータ技術を開発することや、コンピュータ技術を応用して社会を便利にすることは、情報科学がなければできないのです。
情報科学部を出た場合に、どのような就職先が良いと考えますか?
今の世の中で、コンピュータ技術が使われていない分野はありません。その意味で、どのような分野へ就職しようと、情報科学部で学んだ知識や経験は必ず活かされます。
しかし、あえて具体的な方向性をいくつか示すなら、「情報エンジニアリング」を中心に学ぶ皆さんは、コンピュータ技術のプロになるので、コンピュータシステムを開発する企業に進むと良いでしょう。
「データサイエンス」を中心に学ぶ皆様は、どのような企業に就職しても、歓迎されることでしょう。「ビジネスアナリティック」を中心に学ぶ皆様は、高度な分析が必要な企業に進むと、より満足感が得られるでしょう。
繰り返すようですが、情報科学は未来を創る学問です。どのような就職先でも未来を創る仕事を任されます。結局、コンピュータ技術を使って何を成し遂げたいかで進路を決めた方が良いでしょう。
大学の先生の中に実務家教員という人たちがいるようですが、どのような教員ですか?
最近まで民間企業や公共機関などで仕事をしてきた人です。教員経験が長い人と比べて教育経験は浅いですが、実際に企業や公共機関でコンピュータ技術がどのように使われているのかを熟知しています。
そのことから、実践的な教育が期待されています。皆さんが就職して社会に出ていく際に、どのような知識や技術が即戦力になるかを考えて、今までの大学教育にはなかった新たな教育プログラムを作っていくことが望まれています。
私たちが社会に出ていくころにAIはどのように進化していますか?
AIの進化スピードは、とてつもなく速いです。他の学問にはないスピードで変化していきます。皆さんが社会に出るころには、もっと汎用的なAIが生まれていることでしょう。
しかし、人間にとって代わるようなAIが生まれているかというと疑問です。あくまで限られた範囲で賢さが進化していくレベルだと思います。
確かに生成AIと呼ばれる技術が生まれて、人間より優れた能力を発揮する場面も出てきました。しかし、そのAIを使いこなすことで、さらに人間の能力が進化するのではないでしょうか。AIを使って、どのように人間の能力を高めていくか。情報科学を学んだ皆さんに与えられた今後の命題かもしれません。
